「大企業で安定して働きたい。」
「障害がある自分には大企業で働くのは難しいのでは…」
障害者雇用で大企業にチャレンジする前に諦めてしまっていませんか?
求人を見れば「契約社員スタート」が多く、スキルや実績が問われることも多いため、不安を感じるのは当然です。
でも実は今、障害者雇用で大企業に就職するチャンスは、確実に広がっています。
私自身も、義足というハンデを抱えながら、悩み・迷い・挑戦を繰り返してきました。
この記事では、障害者雇用で大企業を目指す方に向けて、採用の現実と突破のコツ、そして体験談を交えてお伝えします。
大企業の障害者雇用の現状とは?
障害者雇用において、大企業での採用チャンスはここ数年で確実に広がっています。
その背景には、法改正による法定雇用率の引き上げや、ダイバーシティを推進する社会的な流れがあります。
 義足パパ
義足パパ障害者雇用の現状を詳しく説明していきます。
法定雇用率の引き上げとその影響
2024年4月、民間企業に課される法定雇用率は2.5%に引き上げられました。
さらに2026年には2.7%まで上昇予定です。
| 令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
| 対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40人以上 | 37.5人以上 |
(出典:厚生労働省「障害者の法定雇用率引き上げと支援の強化について」)
つまり、企業にとって障害者の雇用は“やらなければならないこと”になっているのです。
従業員数が多い大企業ほど、その分多くの障害者を雇用する必要があるため、障害者採用枠は拡大傾向です。



現状として、すべての企業が法定雇用率を満たしているわけではありませんが、障害者の正社員雇用はチャンスが広がっています!
法定雇用率を達成できない企業には、行政指導や納付金制度(罰則)が課されることもあるため、企業側も本気で取り組んでいます。
特例子会社と一般企業の違い
大企業の障害者雇用といえば、特例子会社の存在も見逃せません。
特例子会社とは、障害者の雇用を目的として設立された企業で、親会社の子会社として運営されます。
■ 特例子会社
- 障害者雇用を目的に設立されたグループ会社
- バリアフリーや業務サポートが整っており、就労支援に特化した環境
■ 一般企業(親会社・本体)
- より多様な職種があり、キャリアアップや昇進の可能性も高い
- ただし業務の専門性や責任が求められるため、選考ハードルはやや高め



私も転職活動中、特例子会社と本体採用の両方を検討しました。
「安心して働きたいか」「スキルを活かして成長したいか」など、自分の希望と適性に合わせて選択しましょう。
大企業の障害者雇用で働くメリット
ここでは、障害者雇用で大企業に勤めることで得られる主なメリットを3つ紹介します。



自身の経験もふまえながら、解説していきます。
制度・設備が整っている
大企業の多くは、障害者が働きやすいように制度や環境面の整備が進んでいます。
具体的には以下のようなポイントがあります。
- バリアフリー設計(スロープ、エレベーター、多目的トイレなど)
- 時短勤務やフレックス制度
- 障害者向けの研修・メンター制度
私が現在働いている企業も、入社前に職場のバリアフリー環境やサポート体制について説明があり、安心してスタートを切れました。
給与・福利厚生が手厚い
大企業では、給与水準が比較的高めで、福利厚生も非常に充実しています。
- 昇給・賞与あり
- 通勤手当、住宅手当、家族手当などの支給
- 社会保険・企業年金・退職金制度など
「障害者雇用=非正規で待遇が悪い」というイメージがあるかもしれませんが、大企業であれば経済的にも安定した暮らしを目指すことが可能です。
安定した給与や福利厚生があれば、結婚や家族との生活を現実的に考えやすくなります。
障害があっても結婚できるのか?不安を感じている方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。
▼あわせて読みたい
障害者でも結婚できる?現実と乗り越えるためのポイントを解説!
キャリアアップの道がある
障害者雇用といえども、やる気と実力次第でキャリアアップできる企業も増えています。
障害者雇用枠で入社して、数年後には主任や係長といったポジションに昇進した方もいます。



責任やプレッシャーはありますが、やりがいにもつながるでしょう。
大企業は評価制度が整っていることが多く、キャリアアップを目指しながら長期的に働きたい人には大きなメリットです。
大企業の障害者枠で働くときの気をつけたいポイント・落とし穴
大企業とはいえ、実際に働きやすい環境かどうかは別問題です。
実際に就職や転職活動をした中で感じた「気をつけるべき点」も正直にお伝えします。
選考倍率・採用ハードルが高い
大企業は人気が高く、障害者雇用枠求人に多数の応募が集まり、倍率は高くなります。



私も複数社に応募しましたが、面接まで進めずに終わった企業もありました。
特に「最初から正社員で採用されたい」と考える方が多く、選考の競争率は高くなりがちです。
しかし、大企業の一般雇用枠と比較すると、実は障害者雇用枠の方が就職しやすいケースもあるのです。
一般雇用の場合は離職率が低く、求人がなかなか出ません。また、倍率の高さは障害者雇用枠と同等かそれ以上です。
大企業は人気があり、障害者雇用枠だけがハードルが高いわけではないので、積極的に経験や資格をアピールしていきましょう。
現場のバリアフリー状況には差がある
求人票や本社の見学ではバリアフリー完備のように見えても、実際に配属される予定の部署や拠点では環境が整っていないケースもあります。
私が面接を受けたある会社では、本社はピカピカのバリアフリーオフィスでしたが、実際の勤務先になる予定だった工場にはスロープもエレベーターもなく、「これは無理だ…」と判断して辞退しました。



こうした情報は現地で初めてわかることも多いため、実際に職場を見たり、働いている人の声を聞いたりすることが非常に大切です。
表向きだけの「数合わせ採用」も存在する
法定雇用率を満たすために、形式的に障害者を採用しているだけの企業も残念ながら存在します。
そうした企業では、面接で具体的な業務の話がなく、「とりあえず来てくれればOK」というような印象を受けました。
入社してもフォロー体制が整っておらず、結果的に孤立して辞めてしまう…という話も耳にします。
雰囲気で感じることもありますが、面接時に「どんな仕事をするのか?」「配慮は具体的にどうしてもらえるのか?」を確認することが、後悔しないためのカギです。
障害者雇用で大企業に採用されるための5つの戦略
「大企業に入りたい」と思っても、ただ求人を待つだけではチャンスは広がりません。
特に障害者雇用枠では、情報収集・企業選び・自己PRの仕方が、採用の成否を大きく左右します。
ここでは、実体験をもとに、大企業への採用につながった5つの実践ポイントをご紹介します。
- 複数の転職サイトに登録して情報収集する
- 公式サイト経由での応募も視野に入れる
- 企業選びは求人票だけで決めないことが失敗を防ぐ
- 入社前に“毎日働けるか”を体感しておこう
- 「経験」「できること」「配慮」をセットで伝える



それぞれ解説していきます!
複数の転職サイトに登録して情報収集する
障害者向けの転職サイトには、それぞれ異なる求人が掲載されているため、複数登録することで選択肢が広がります。
代表的なサイト:
- dodaチャレンジ
- ウェブサーナ
- マイナビパートナーズ紹介



私も最初は3つ以上のサイトに登録し、それぞれの非公開求人やスカウト情報を活用していました。
正直、担当者の対応にバラつきがあると感じる場面もありました。「合わない」と感じたら他のサイトへ切り替える柔軟さが大切ですよ。
また、求人の詳細は似ていても、サイトによって募集職種や勤務地が微妙に違うこともあります。
時間と手間はかかりますが、“良い求人”は一つのサイトだけでは見つからないのが現実です。
公式サイト経由での応募も視野に入れる
転職サイトからの応募だけでなく、企業の公式ホームページから直接応募する方法も有効です。



私が現在働いている航空会社も、最終的には公式サイトの採用ページから応募しました。
当時は転職サイトにも掲載がありましたが、公式からの方が詳細情報が多く、会社の雰囲気や業務内容が明確に伝わってきました。
また、企業側にとっても転職エージェント経由より、直接応募者の方が採用コストがかからないため、場合によってはプラスに働く可能性があります。
実際のところ、採用後に人事担当と話したときに「同じようなスキル・経験の人が複数いた場合、直接応募の方が採用されやすいのでは?」と感じました。
企業選びは求人票だけで決めないことが失敗を防ぐ
求人票に書いてある条件だけで企業を選ぶと、「こんなはずじゃなかった…」という事態にもなりかねません。
私は、友人が勤務している企業について事前に話を聞けたことが、会社選びの大きな決め手になりました。



実際に働いている人の声ほど信頼できる情報はありません!
また、面接の際には「どんな部署に配属されるのか?」「勤務地はどこか?」をしっかり確認することが大切です。
できれば職場見学をお願いし、現場の雰囲気やエレベーターの有無、トイレの状況などをチェックしておくと安心できる職場環境だと感じられるはずです。
入社前に“毎日働けるか”を体感しておこう
企業選びで意外に見落としがちなのが、「毎日の通勤が自分の体力・体調に合うか」という点です。
実は、ある企業で最終面接まで進みましたが、通勤ラッシュが想像以上に過酷で辞退したことがあります。



採用前の段階で、志望する企業の始業時間に合わせて電車に乗ってみたところ「毎日は無理だ」と感じました。
特に身体に障害がある場合、ぎゅうぎゅうの満員電車で長時間立ちっぱなしは大きな負担です。
「無理なく通えるか?」という視点で確認しておくと、入社後のストレスを大きく減らせます。
「経験」「できること」「配慮」をセットで伝える
応募書類や面接では、「障害があること」よりも、「どのように働けるか」「どんなスキルがあるか」を具体的に伝えることが大切です。
特に大企業では、安定的に業務をこなせる人材を求めています。
以下の3点を整理しておくと効果的です。
- 経験・実績:どんな仕事をしてきたか、どのような成果を出したか
- できること:自分の得意分野、どんな貢献ができるか
- 配慮が必要なこと:どのような配慮があれば働けるか、逆に不要な配慮はあるか
企業側も「どこまで配慮すればいいかわからない」と不安を抱えている場合があります。
だからこそ、自分から丁寧に伝えることが信頼につながり、職場での定着にも役立ちます。



障害者雇用の場合もスキルや資格があれば優位に働きますので、しっかりアピールしましょう。
まとめ:行動すれば道は開ける
「大企業で働くなんて、障害がある自分には無理かもしれない」と感じていたとしても、今は状況が変わりつつあります。
法定雇用率の引き上げやダイバーシティ推進の流れを受けて、多くの大企業が障害者雇用に本気で取り組み始めているからです。
もちろん、選考の競争率や職場環境のギャップなど、注意すべきポイントはあります。
ですが、情報をしっかり集め、自分に合った職場を見極める目を持てば、障害があっても安心して長く働ける環境を見つけることは十分可能です。
私自身、試行錯誤の末にたどり着いた現在の職場で、毎日やりがいを感じながら働けています。



大切なのは、「自分には無理かも」と思い込まず、少しずつでも行動してみることです!
あなたにも、きっと可能性があります。
まずは、できることから一歩ずつ始めてみてください。
自分に合った障害者向けの求人を見つけたい方へ
① 障害者の就職・転職なら【dodaチャレンジ】
② 障害者就職・転職・キャリアアップのご相談は【株式会社U三へ】


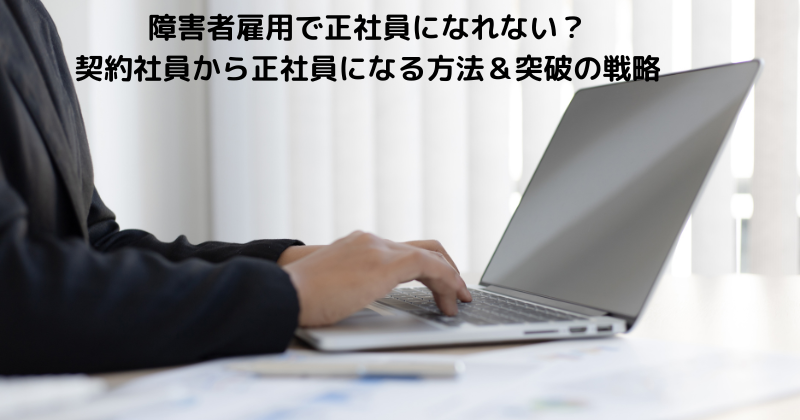
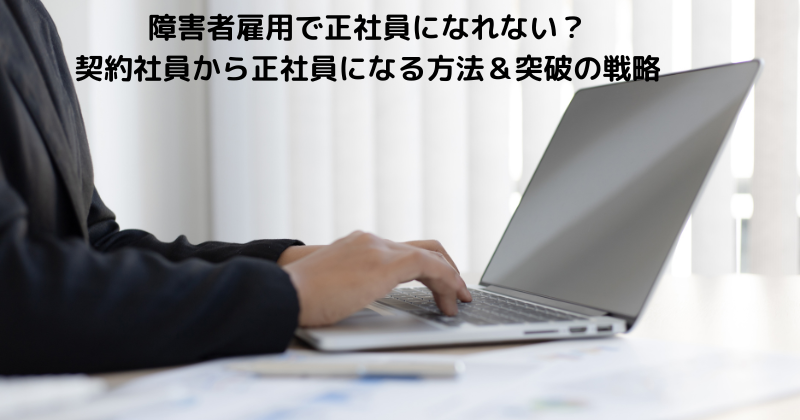


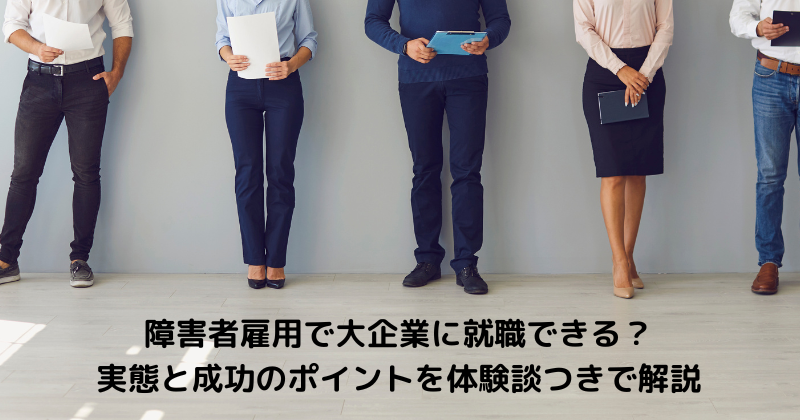





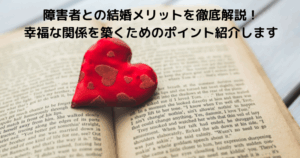

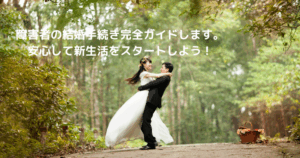
コメント