「5年以上働いても正社員になれない…」
「正社員登用の話なんて一度も出ない」
障害者雇用で働く中で、こうした悩みを抱えている方は少なくありません。
一方で、正社員になれる人もいるのが現実です。
では、正社員になれる人となれない人の違いは何なのでしょうか?
実は、企業の採用基準を理解し、戦略的に行動することで、正社員への道が開けるケースもあります。
この記事では、障害者雇用の現状や、正社員になるための方法を解説します。
さらに、筆者自身が正社員を勝ち取った戦略も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
【現状】障害者雇用で正社員になれない?障害者雇用の正社員率
厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査」によると、障害の種類によって正社員の割合に大きな差があります。
- 身体障害者:59.3%(無期53.2%+有期6.1%)
- 精神障害者:32.7%(無期29.5%+有期3.2%)
- 知的障害者:20.3%(無期17.3%+有期3.0%)
出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果」
精神障害者や知的障害者の約7割が契約社員やパートのままというのが現実です。
また、大企業では比較的正社員雇用が進んでいるものの、中小企業では契約社員のまま働き続けるケースが多い傾向があります。
【問題点】障害者雇用で契約社員のままになりやすい3つの理由
企業が障害者雇用を「契約社員スタート」とする背景には、いくつかの本音があります。
なぜ正社員として採用されにくいのか、その背景には大きく3つの理由があります。
- 企業の受け入れ態勢が未熟
- 体調の波や休職リスクを懸念される
- 本人の不安や自己評価の低さ
詳しく見ていきましょう。
企業の受け入れ態勢が整っていない
企業の多くは、障害者雇用のノウハウが不足しているため、適切な業務の割り振りや職場環境の整備が不十分です。
具体的には、以下のような問題があります。
- バリアフリー設備が整っていない
- 理解や配慮不足による職場適応の難しさ
- 障害者雇用=業務の負担増と考える企業も多い
こうした理由から、企業は慎重になりがちです。
体調の波や休職リスク
正社員の場合は、フルタイム勤務が基本のため、長時間勤務が不安要素になります。
また、精神障害者の休職率は高い傾向にあり、企業側も慎重になりがちです。
結果として、以下のような対応が取られます。
- まずは契約社員として様子を見る
- 長時間勤務を避けるため非正規雇用にとどめる
また、障害者本人も、体調や職場環境が合うか不安を感じることがあります。
そのため、企業側が慎重になるケースもあれば、本人の希望で非正規を選ぶ場合もあります。
本人の不安や自己評価の低さ
「自分は正社員としてやっていけるのか?」と不安を抱く障害者の方は少なくありません。
そのため、昇進や正社員登用を希望しづらい傾向があります。
特に、以下のような思い込みが影響します。
- 障害者だから正社員は無理という固定観念を持ってしまう
- チャレンジする前に諦めてしまう
自信を持ってアピールしなければ、企業は「正社員を希望していない」と解釈することもあります。
【メリット】障害者雇用で正社員になる3つのメリット
正社員になるメリットは「給与・安定・キャリア」の3つが挙げられます。
- 安定した雇用と給料アップ
- 社会的信用が高まり、将来設計がしやすい
- キャリアアップやスキル向上の機会が増える
安定した雇用と給料アップ
正社員は、契約社員やパートに比べて解雇されにくく、雇用が安定しています。
毎月の給与が安定しているだけでなく、昇給や退職金の制度が整っている企業も多く、ボーナスがあれば一度に何十万円もの追加収入が得られます。
貯金を増やしたり、旅行や趣味にお金を使ったりと、生活の幅が広がることでしょう。
社会的信用が高まり、将来設計がしやすい
正社員になると、社会的な信用が向上し、住宅ローンやクレジットカードの審査が通りやすくなります。
契約社員の場合、収入が不安定なため、将来の計画を立てにくいと感じている人も多いでしょう。
しかし、正社員なら昇給やボーナスも見込めるため、マイホーム購入や老後の備えなど、長期的な目標を考えやすくなります。
キャリアアップやスキル向上の機会が増える
正社員になると、研修や昇進のチャンスが増え、スキルアップしやすい環境が整います。
また、契約社員やパートに比べて責任のある仕事を任される機会が増え、経験や実績を積めば、社内での評価が上がり、昇進や昇給のチャンスも増えます。
「今後のキャリアをしっかり築きたい」と考えている人にとって、正社員は大きなメリットがある働き方といえるでしょう。
【デメリット】正社員になることで注意するべき2つのこと
一方で、正社員になるデメリットも存在します。
- 責任やプレッシャーが大きくなる
- 柔軟な働き方が難しい
責任やプレッシャーが大きくなる
正社員は契約社員やパートに比べて、業務の範囲が広がり、責任が増えることが一般的です。
企業側も長期的な戦力として期待するため、重要な業務を任されることが多くなります。
しかし、業務量が増えたり、厳しい納期に追われたりすると、ストレスが溜まりやすく、大きな負担に感じることも。
最悪の場合、体調に影響がでてしまう可能性もあるでしょう。
柔軟な働き方が難しい
正社員は勤務時間が固定されることが多く、契約社員やパートと異なり柔軟な働き方は難しくなります。
フレックスタイム制やテレワークを導入している企業は増えているものの、まだ少数派です。
さらに、業務の状況によっては、残業を求められることもあります。
繁忙期には長時間労働が続くことがあり、フルタイム勤務に加えて残業が重なると、精神的にも体力的にも負担が大きくなります。
そのため、正社員として働く場合は、自分の体調やライフスタイルに合った働き方ができるかどうかを事前に確認することが重要です。
【解決策】障害者雇用で正社員になるための具体的な方法
障害者雇用で正社員を目指す方法は、大きく分けて2つあります。
- 最初から正社員求人に応募する
- 契約社員として働き、正社員登用を目指す
どちらの方法が適しているかは、職種や企業の方針によって異なります。
また、正社員を目指すなら、大企業の障害者雇用に注目するのも一つの選択肢です。
それぞれ詳しく解説していきます。
最初から正社員求人に応募する
1つ目は、正社員採用の求人を見つけることです。
就職や転職活動の際に、最初から正社員枠に応募し、採用を目指す方法です。
しかし、障害者の正社員求人数は、依然として少ないのが現状です。
また、以下の理由でハードルが高くなりがちです。
- 職種が限られる
- 採用条件が厳しい
- 競争率が高く、簡単には採用されない
そのため、正社員を目指す場合、転職エージェントや専門の求人サイトを活用し、幅広く求人情報を集めましょう。
契約社員として働き、正社員登用を目指す
2つ目は、契約社員として働き、正社員登用を目指す方法です。
障害者雇用では、契約社員やアルバイトからスタートする求人が多くあります。
この方法なら、実際に働きながら業務や職場環境に慣れていけるので、企業側も求職者側も安心してステップアップできます。
ただし、正社員登用が確約されているわけではない点には注意が必要です。
企業によっては、登用の時期や基準が明確でない場合もあるので、事前に正社員登用の実績や条件は必ず確認しておきましょう!
最初から正社員として働くことに不安を感じるなら、非正規からのスタートも選択肢の一つです。
狙い目!大企業の障害者雇用の現状
障害者雇用で正社員になりたいなら、大企業を狙うのも有効な戦略です。
法定雇用率の引き上げによって、特に大企業では障害者の正社員雇用は増加傾向です。
2024年4月1日から、民間企業の法定雇用率は2.5%に引き上げられました。
例えば、従業員40人以上の企業の場合、最低1人の障害者を雇用する義務があります。
つまり、従業員数が多い大企業ほど、障害者雇用の採用枠が多いことになります。
法定雇用率とは、一定規模以上の企業が雇用する障害者の割合を定めた基準です。
企業は、この割合以上の障害者を雇用する義務があります。
正社員を目指すなら、選択肢の一つとして検討する価値があるでしょう。
【体験談】義足の筆者が語る!障害者雇用で正社員になった道のり
私は義足の障害者として、公務員の障害者採用枠でキャリアをスタートしました。
約10年間、公務員として働いた後、大手航空メーカーに転職しました。
どちらも最初から正社員として採用されました。
転職のときも、最初から正社員として採用されたのは、「スキルを証明できた」ことが大きかったと思います。
- 資格を取得:日商簿記1級などを取得し「戦力になる」と思わせる
- 実績をアピール:公務員時代の安定した勤務経験を強調
- できることを明確化:「障害の有無」ではなく「自分の強み」を企業に伝える
障害者でも、優れたスキルや経験を持つ人は多くいます。
だからこそ、「自分はこれができる!」と強みを明確にすることが大切です。
【まとめ】契約社員のまま?大企業の障害者雇用を活用しよう!
障害者雇用では契約社員のまま働き続けるケースが多いですが、正社員登用は決して不可能ではありません。
企業が求めるスキルを身につけ、「正社員登用実績のある企業」や「障害者雇用に積極的な大企業」を選ぶことが、正社員への近道になります。
特に、大企業では法定雇用率を満たすため、障害者の正社員雇用が進んでいるため、狙い目の一つです。
あなたのキャリアの可能性を広げるために、ぜひチェックしてみてください!
「障害があるから正社員は無理」と諦めず、できることからまず一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
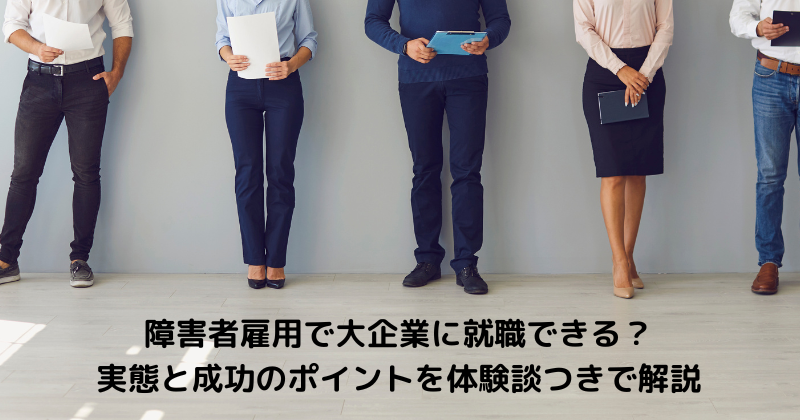

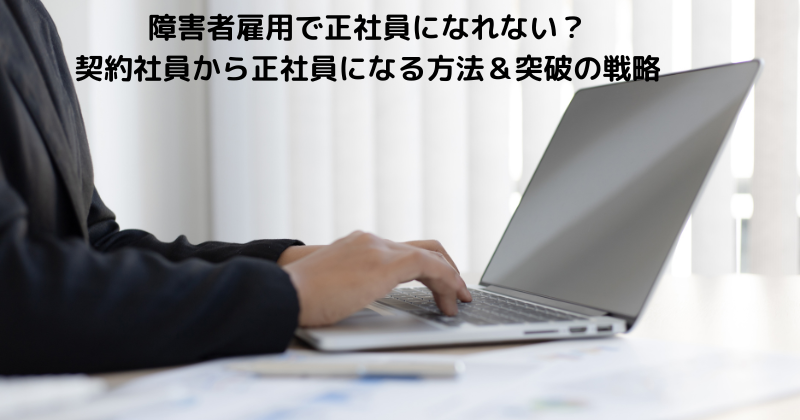





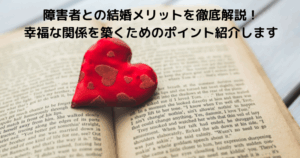

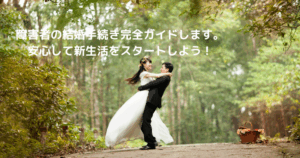
コメント